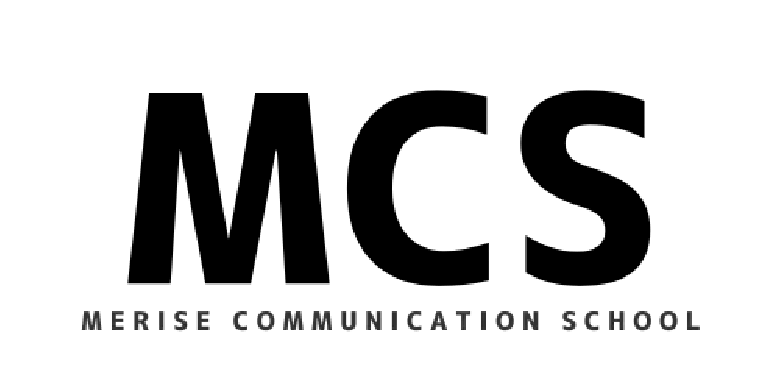News
お知らせ一覧
こんにちは。
発達障がい・不登校など学びづらさを抱える小学生・中学生・高校生のための個別学習塾「ラーンメイト」です。
生活リズムが崩れているという声をよく聞きます。
夜更かしをしてしまったり、朝起きられなかったり……。
お子さまが、午前中は調子が悪く日中はごろごろとしていて、
夕方や夜になって元気がでてくる、という様子を見ると、
「怠けているだけではないか?」と感じる方もいらっしゃると思います。
そこには、思春期前後の発症が多い「起立性調節障害」という病気が
隠れているかもしれません。
今回は、その「起立性調節障害」についてお話しします。
起立性調節障害とは?
起立性調節障害には、
・立ちくらみやめまい
・寝起きが悪い
・頭痛や腹痛
・倦怠感
・食欲不振
など、様々な症状があります。
そして、その訴えがあるにも関わらず、
臓器などには病気が認められないものを言います。
症状がよくあらわれるのは、
・小学校高学年から中学生年代
・春から初夏にかけて
だと言われています。軽症例を含む有病率は、
小学生の約5%、中学生の約10%であり、
不登校の約3~4割に起立性調節障害を併存すると言われています。
起立性調節障害の発症には、
内臓や血管などの働きをコントロールし、
体内の環境を整える「自律神経」が大きく関わっています。
思春期のお子さまは、からだが急速に大きくなるため、
からだと自律神経のバランスが崩れやすくなっています。
全身の血液の動きを調節する自律神経のバランスが崩れることで、
特に上半身や脳への血流低下が起こり、
立ちくらみや気分不良、重症の場合は失神などが起こることがあります。
また、思春期前後のお子さまは、
精神面の影響により自律神経が乱れやすいという特徴があります。
季節や気候の変化、生活リズムの乱れ、ストレスなどが、
発症や悪化において複雑に影響を及ぼすのです。
起立性調節障害の治療
生活習慣の改善や、起立時に頭を下げてゆっくり起立する、
などの日常生活上の工夫が必要です。
また、重症度などに応じて薬を使った治療を行います。
いずれにしても、
「起立性調節障害は身体疾患であり、根性や気持ちの持ちようだけでは治らない」
ということを、ご本人と保護者の方や周囲の人が理解することが重要です。
お子さまの様子を見て、「怠けているのかな」と感じるときは、
もしかしたら「起立性調整障害」という病気かもしれない、
ということを知っておいていただければと思います。